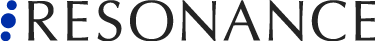-

お六櫛 手挽き すき櫛 大深角
¥36,000
予約商品
木曽が誇る伝統工芸品「お六櫛」。 長野県の伝統的工芸品(14品目)として指定されている、300年以上受け継がれてきた伝統と技、そして職人の技が光る貴重な櫛です。 こちらは、硬くて加工が困難な、柞(いす)の木を用い、熟練の職人によって一つひとつ手作業で仕上げられた逸品です。 [歴史と由来] 1700年、木曽美人として名高かった「お六」さんは頭痛に悩まされていました。 御嶽山に祈願したところ「みねばりの木で櫛を作り髪を梳きなさい」という御告げを受け、実行すると頭痛が治ったといわれています。 以来、「お六櫛」と名付けられたこの櫛は、「みねばり」「つげ」「柞(いす)」の木を用いて作られ続けています。 [職人の技] 「道具を身体の一部とし、心で挽く」 櫛歯を梳くための道具も各々が使いやすいように自分たちで作り、調整し、ミリ単位以下の間隔で一本一本の櫛歯を丁寧に梳いていきます。 この櫛を手がけた職人は「鉋を意識して挽くうちは、良い歯挽きはできない。身体全体で挽くようになり、心で挽かなくては使う人の心の望む血の通った櫛はひけない」という恩師の教えを胸に日々精進しています。 [皇室御用達の品格] 本商品を制作した職人は、皇后陛下が祭祀の際にお使いになる櫛も手がけた名工です。 高齢となった今も技を磨き続け、限られた作品を全国の展示会で発表しています。 多くのお店様からお取引を打診されているそうですが、基本的にお断りしていることもあり、名前は載せないで欲しいとのご希望されているため、お名前は伏せさせていただきますこと、ご了承ください。 [希少価値] お六櫛の素材となる木は、櫛として使えるまでに100年ほどの成長が必要です。 現在は行政方針により伐採が制限され、長野県外の木材も密度不足で適していないため、素材の確保が極めて困難になっています。 職人の減少と相まって、お六櫛は年々希少価値を増しています。 [素材について] こちらの櫛は、「柞(いす)」という木から作られています。 「柞(いす)」の木は、家具や木工品にも使われるほど強度に優れた木材で、長く使っても歪みにくく、丈夫さが魅力です。 その反面、とても硬いため、加工には熟練の技術と時間が必要とされます。 木目は力強く、年輪がはっきりと現れ、重厚で深みのある色合いも特徴のひとつ。 自然の風合いをそのままに、しっかりとした存在感を持つ、味わい深い素材です。 [商品詳細] 素材: 柞(いす) 製法: 伝統的手法による完全手作業 産地: 長野県木曽地方 サイズ: 約12cm×約6cm ※ケース付き 櫛歯: 極細歯(ストレートヘアが最適です) [お手入れ方法] ・椿油などを布(木綿・ガーゼ)などに染み込ませて拭いてください。 (木製のため、椿油は持ち手の背に少量塗るだけで、適量が歯の方へと自然に染みていきます。) ・櫛の歯の間に汚れが溜まった場合は、ブラシなどで掃除しますときれいになります。 ・湯水で洗ったり、濡らしてしまうと、木の油分が取れてしまうます。また、曲がったり通りが悪くなるので、ご注意ください。 ・長年使用していただきますと、色つやが更に増して、使い心地も一層格別になります。 ・天然の木でできた櫛です。落としたり、ぶつけてしまったりするなど強い衝撃が加わると、割れてしまうことがございますのでご注意ください。 [ご購入にあたって] 職人の高齢化と材料不足により生産数が限られております。伝統工芸の保存にご理解いただける方に、心を込めてお届けいたします。 この商品は交渉の末、特別に当サイトのために販売していただいた貴重な一品です。
-

お六櫛 とかし櫛 5寸
¥31,000
予約商品
木曽が誇る伝統工芸品「お六櫛」。 硬くて加工が困難な、柞(いす)の木を用い、熟練の職人によって一つひとつ手作業で仕上げられた逸品です。 300年以上受け継がれてきた伝統と技、そして職人の技が光る貴重な櫛をご案内します。 [歴史と由来] 1700年、木曽美人として名高かった「お六」さんは頭痛に悩まされていました。 御嶽山に祈願したところ「みねばりの木で櫛を作り髪を梳きなさい」という御告げを受け、実行すると頭痛が治ったといわれています。 以来、「お六櫛」と名付けられたこの櫛は、「みねばり」「つげ」「柞(いす)」の木を用いて作られ続けています。 [職人の技] 「道具を身体の一部とし、心で挽く」 櫛歯を梳くための道具も各々が使いやすいように自分たちで作り、調整し、ミリ単位以下の間隔で一本一本の櫛歯を丁寧に梳いていきます。 この櫛を手がけた職人は「鉋を意識して挽くうちは、良い歯挽きはできない。身体全体で挽くようになり、心で挽かなくては使う人の心の望む血の通った櫛はひけない」という恩師の教えを胸に日々精進しています。 [皇室御用達の品格] 本商品を制作した職人は、皇后陛下が祭祀の際にお使いになる櫛も手がけた名工です。 高齢となった今も技を磨き続け、限られた作品を全国の展示会で発表しています。 多くのお店様からお取引を打診されているそうですが、基本的にお断りしていることもあり、名前は載せないで欲しいとのご希望されているため、お名前は伏せさせていただきますこと、ご了承ください。 [希少価値] お六櫛の素材となる木は、櫛として使えるまでに100年ほどの成長が必要です。 現在は行政方針により伐採が制限され、長野県外の木材も密度不足で適していないため、素材の確保が極めて困難になっています。 職人の減少と相まって、お六櫛は年々希少価値を増しています。 [素材について] こちらの櫛は、「柞(いす)」という木から作られています。 「柞(いす)」の木は、家具や木工品にも使われるほど強度に優れた木材で、長く使っても歪みにくく、丈夫さが魅力です。 その反面、とても硬いため、加工には熟練の技術と時間が必要とされます。 木目は力強く、年輪がはっきりと現れ、重厚で深みのある色合いも特徴のひとつ。 自然の風合いをそのままに、しっかりとした存在感を持つ、味わい深い素材です。 [商品詳細] 素材: 柞(いす) 製法: 伝統的手法による完全手作業 産地: 長野県木曽地方 サイズ: 5寸(約15cm×約4cm) ※ケース付き 櫛歯: 細歯(ストレートヘアが最適です) [お手入れ方法] ・椿油などを布(木綿・ガーゼ)などに染み込ませて拭いてください。 (木製のため、椿油は持ち手の背に少量塗るだけで、適量が歯の方へと自然に染みていきます。) ・櫛の歯の間に汚れが溜まった場合は、ブラシなどで掃除しますときれいになります。 ・湯水で洗ったり、濡らしてしまうと、木の油分が取れてしまうます。また、曲がったり通りが悪くなるので、ご注意ください。 ・長年使用していただきますと、色つやが更に増して、使い心地も一層格別になります。 ・天然の木でできた櫛です。落としたり、ぶつけてしまったりするなど強い衝撃が加わると、割れてしまうことがございますのでご注意ください。 [ご購入にあたって] 職人の高齢化と材料不足により生産数が限られております。伝統工芸の保存にご理解いただける方に、心を込めてお届けいたします。 この商品は交渉の末、特別に当サイトのために販売していただいた貴重な一品です。
-

お六櫛 とかし櫛 4寸
¥17,000
予約商品
木曽が誇る伝統工芸品「お六櫛」。 みねばりの木を用い、熟練の職人によって一つひとつ手作業で仕上げられた逸品です。 300年以上受け継がれてきた伝統と技、そして職人の技が光る貴重な櫛をご案内します。 [歴史と由来] 1700年、木曽美人として名高かった「お六」さんは頭痛に悩まされていました。 御嶽山に祈願したところ「みねばりの木で櫛を作り髪を梳きなさい」という御告げを受け、実行すると頭痛が治ったといわれています。 以来、「お六櫛」と名付けられたこの櫛は、「みねばり」「つげ」「柞(いす)」の木を用いて作られ続けています。 [職人の技] 「道具を身体の一部とし、心で挽く」 櫛歯を梳くための道具も各々が使いやすいように自分たちで作り、調整し、ミリ単位以下の間隔で一本一本の櫛歯を丁寧に梳いていきます。 この櫛を手がけた職人は「鉋を意識して挽くうちは、良い歯挽きはできない。身体全体で挽くようになり、心で挽かなくては使う人の心の望む血の通った櫛はひけない」という恩師の教えを胸に日々精進しています。 [皇室御用達の品格] 本商品を制作した職人は、皇后陛下が祭祀の際にお使いになる櫛も手がけた名工です。 高齢となった今も技を磨き続け、限られた作品を全国の展示会で発表しています。 多くのお店様からお取引を打診されているそうですが、基本的にお断りしていることもあり、名前は載せないで欲しいとのご希望されているため、お名前は伏せさせていただきますこと、ご了承ください。 [希少価値] お六櫛の素材となる木は、櫛として使えるまでに100年ほどの成長が必要です。 現在は行政方針により伐採が制限され、長野県外の木材も密度不足で適していないため、素材の確保が極めて困難になっています。 職人の減少と相まって、お六櫛は年々希少価値を増しています。 [素材について] こちらの櫛には、「みねばり」と呼ばれる木が使われています。 みねばりは、粘りがありながら非常に硬く、折れにくい特性を持つため、古くから櫛や細工物に最適な素材とされてきました。 加工は繊細ですが、仕上がった木肌はなめらかで手に馴染みやすく、使うほどに艶が深まり、飴色へと変化していきます。 また、木目は細かく美しく、落ち着いた上品な風合いも魅力のひとつです。 自然のやさしさと、職人の技が調和した、時を重ねて育つ櫛です。 [商品詳細] 素材: みねばり 製法: 伝統的手法による完全手作業 産地: 長野県木曽地方 サイズ: 4寸(約12cm×約4cm) ※ケース付き 櫛歯: 細歯(ストレートヘアが最適です) [お手入れ方法] ・椿油などを布(木綿・ガーゼ)などに染み込ませて拭いてください。 (木製のため、椿油は持ち手の背に少量塗るだけで、適量が歯の方へと自然に染みていきます。) ・櫛の歯の間に汚れが溜まった場合は、ブラシなどで掃除しますときれいになります。 ・湯水で洗ったり、濡らしてしまうと、木の油分が取れてしまうます。また、曲がったり通りが悪くなるので、ご注意ください。 ・長年使用していただきますと、色つやが更に増して、使い心地も一層格別になります。 ・天然の木でできた櫛です。落としたり、ぶつけてしまったりするなど強い衝撃が加わると、割れてしまうことがございますのでご注意ください。 [ご購入にあたって] 職人の高齢化と材料不足により生産数が限られております。伝統工芸の保存にご理解いただける方に、心を込めてお届けいたします。 この商品は交渉の末、特別に当サイトのために販売していただいた貴重な一品です。